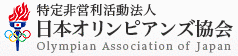- トップページ
- オリンピアンインタビュー
- 第3回 猪谷千春さん
【3:第二の人生 ~ アメリカンホーム保険社長に】
ビジネスでもトップになる
高橋:ビジネスに入ったときの、ロールモデルはスターさんになのかなと思ったのですが…。あるいはまた特に目標とされていらっしゃる方はいなかったんですか?
猪谷:もう全然そういうことは。まあ、全く無かったら嘘なのかもね。やっぱり会社の長になる、つまりオリンピックでもメダリストになるっていうこと、それをそのまんま第二の人生にも持って入るということで、その分野でもってメダリストになろうという気持ちがメダリストは何かって言えば、それは会社のトップになるということだよね。
高橋:日本での就職というのもお考えになったようですが、結局はアメリカで就職された。それは日本の企業では実力が発揮できないとその時お考えに。
猪谷:本当にそうなの。あのう、まだこの頃は、一番最初がやっぱり外交官になりたかったわけね。だけれども、東大出て無いと大使にはなれなかったのね。僕がなれたかどうかは別として。そんな先の見えてるところは嫌なんだよね。それから、とにかくインターナショナルなところに勤めたいと。で、当時JALがそうだったから。で、JALにちょっと触手を動かしたんだけど、当時部長職以上はもう皆官界からのスベリだったんだよね。で、これも先が見えているから止めて。要するにそういう状態がずうっとあったもんだから。
高橋:非常に閉ざされた世界。
猪谷:うん。閉ざされたことなんだよね。ことインターナショナルに関してはね。
高橋:今はどうですか?
猪谷:今はそんなことは無いよ。
高橋:日本の企業でも十分実力主義でやっていける。
猪谷:そういう会社も多くなったようだよな。
高橋:でもこの時は本当にアメリカのAIUしかなかったということになるわけですね。
猪谷:そうね。
「オリンピアン」としての自分と「ビジネスマン」としての自分
高橋:2年間ニューヨークの本社で厳しい研修を受けられて、1961年にAIU日本支社の傷害保険部初代部長になられたということで。「オリンピアン」としての今までの自分というのと「ビジネスマン」としての自分というのは、別ですか?それともこうオリンピアンとしての自分が土台にあって、その上にビジネスマンとしての自分がある。
猪谷:土台になったかどうか知らないけど、とにかくやればできるんだって言う自信はもっていたよね。だから、2つ目に外に営業に出て行ってもやっぱりメダリストだったっていうことがプラスにはなったよね、やっぱりね。
高橋:ゼロからのスタートというふうにお書きになっていますが、やはりその一方で知名度っていうのがあった。
猪谷:そうそう。
高橋:だから自分ではゼロからのスタート、ビジネスマンとしてゼロからやるんだっていう気持ちはあったけれども、実際には知名度であったり、あるいは自分の中の自信というのがあった。
猪谷:要するにビジネスの中ではゼロだよね。そのサラリーマンとして自信だとかそれから知名度というものがあった、これがプラスになったということで、ビジネスをゼロから始めたっていうのは間違いない。
高橋:一つこれだけのものを極められたという自信があれば他の事はできるだろうという、そういった自信。
猪谷:他のこともできるという。
ビジネスにおけるグローバルスタンダードと日本の風土
高橋:傷害保険という考え方が日本の風土に適合するかという疑問があったそうですが、特に当時戦後のインフレで保険や預貯金に対する国民のアレルギーが大きかったそうですね。そこでお聞きしたいのは、ニューヨークで2年間の厳しい研修を受けられたという、そのアメリカの研修というのがどれほどその当時の日本の風土に合ったのかなっていう疑問があるのですが…。
猪谷:合わない、全然。
高橋:ですよね。
猪谷:で、それを合わせるように変えていったわけね。
高橋:それは猪谷さんご自身で変えていったんですか?
猪谷:僕自身も変えて行ったし、また、部下やなんかも、それからニューヨークからのいろんな助言もあって変えていってね。例えばその、まあ、あのう、うちは海外旅行傷害保険に非常に重きを当時置いていたわけね。今は海外に支店があるから。そうするとどういうことをしたかと言うと例えばあの頃エクスチェンジレート360円だよね。だからそうすると3,000万で保険を売り出す前に3,600万で出したわけよね。要するにバタ臭い所を表に出しちゃったわけ、却って。
高橋:ほう。表に出しちゃったわけですか?
猪谷:却ってね。それでうちはアメリカの会社なんだということを出していったんだけれども。そういうやり方もある。うん。
高橋:でも、AIUという会社自体が、1919年にスター氏が上海でAAUを設立して、現地の中国人向けに生命保険を売ったことから出発して。それから東南アジア、アメリカ、ラテンアメリカというふうにグローバルに展開して行ってるわけですから、全く日本とか他の文化を知らないアメリカ人の人がアメリカで作った会社とは違いますよね。恐らくAIUという会社自体、それぞれの地域に合うようなマーケティングなり、売り方なり、戦略なりというものを立てていらっしゃったのではないかなと。
猪谷:立てているって言っても理解を示している会社で。
高橋:スターさんが理解を示して。
猪谷:そうそう。
高橋:それは、じゃ、もう猪谷さんにお任せするという形。
猪谷:必ずしもそうじゃないけども、やっぱり日本じゃあんまり経験の無いラインだったから・・。横からのいろんな支援を受けながら商品を構築していった。
高橋:そのままアメリカ式のものを持ち込んでもやはり無理。
猪谷:持ち込んだものもあるし、日本的に変えたものもあるしね。
高橋:具体的に何か例を挙げていただけますか。どういうものがアメリカ式で、どういうものが日本式。
猪谷:それはね、例えばその360を3,600万でやったなんていうのは非常にアメリカ的ないい例だと思うし、それから、そうね、まず日本的なものというと実際に傷害保険に関しては、当初は向うのものを持ち出してやったけれども、しばらく経ってからは、なんて言ったらいいかな、例えばその、黄色い帽子なんて言ったら知らないよね。
高橋:黄色い帽子?
猪谷:昔は小学生は皆黄色い帽子を被って通学してた。
高橋:はい。
猪谷:あれに保険を付けたわけね。つまりあの黄色い帽子を被っていて事故に遭うといくら出しますというようなのね。これなんかもう完全に日本だけのものだから。
高橋:そうですね。
猪谷:外国で黄色い帽子なんていうのはないからね。そういうことだとか。あと、ちょっと技術的なことになっちゃうんだよね。難しいことね。
高橋:何かマニュアルみたいな、お客さんに対する戦略でも良いんですけど…マニュアルはありますか?
猪谷:当然ありますよ。
高橋:アメリカのものがあって、それを日本のものにまた作り変えて。
猪谷:うん。当然日本に合うようにね。
高橋:それは猪谷さんが中心になられて部下の方と一緒に。
猪谷:そうそう。
高橋:何かそこで猪谷さんが重視したこと。日本に傷害保険を浸透させていく、今まで無かったものを浸透させていくということで一番重要だと思ったことっていうのは。
猪谷:いみじくもあなた言われたように、当初生命保険やなんかに対して非常にアレルギーを皆持っていた。なぜならばその、戦前にそれこそ何百円かの保険を付けた、それは今で言えば何百万円に相当したのかも知れないけれども、それが戦争が終わってしまえば紙くず同然になってしまった。だから傷害保険といってもみんな生命保険とオーバーラップしちゃってね、なかなかそのう、理解を示してもらえなかった。そんなことからも当時からやっぱり日本の新聞にはその事故のニュースや何か、自動車事故のニュースだとかあるいはなんかの事故で死んだとか、溺れて死んだとか、いろいろとそういう新聞記事や何かたくさん出たりなんかしてたから、例えばそういうものを保管しておいてね、セールスにはそういうものを使って、生保とは違うんですよというようなやり方でね。アメリカじゃこんなことしなくっても生保と傷害保険は違うということはみんな分かっていたから。だから、要するにそういうマーケットの洗脳から始まるわけよね。
高橋:先ほどわざとアメリカ的な所を出したっておっしゃっていましたけれども、時代的にすごく「アメリカ」が好まれた時ですよね。日本人の中にアメリカの生活に対する憧れがすごくあって、そういう時代だったから、そういう意味でわざとアメリカ的なところを出されたのは逆に良かったのかも知れないですよね。
猪谷:当然その辺は勘定に入れて出したからね。わざとバタ臭さを前面に出して。
高橋:で、尚且つ、実際に売る時には日本の生活に合うような形で商品をだしていく。
猪谷:だから、要するにラインによってはバタ臭さを出して、ラインによっては日本的なものにしていくとかね。
高橋:会社のイメージは、当たり前ですけどアメリカという何かすごく憧れのイメージ。
猪谷:うん、そうそうバタ臭い所を出してね。
社長としてのリーダーシップのとり方
高橋:いろいろご苦労も多かったと思うんですが、1978年にアメリカンホーム保険社長に就任された。47歳という若さで。
猪谷:45歳を逃しちゃった。
高橋:(笑)。すごい。
猪谷:だから、銀メダルかな。(笑)
高橋:社長としてトップに立たれたわけですが、この時に部下とのコミュニケーションやお客さんとのコミュニケーション、あるいはどういったリーダーシップをとって行かれたのですか?
猪谷:それはね和洋折衷しかなかったと思うのね。だから、僕はそれほど昔からのやり方っていうのは、どうしてもリーダーシップを取らなきゃならない時には取るけれども、つまり小泉さんみたいなリーダーシップを取る時もあるけれども、なるべくあれは無くしているわけね。なるべく皆の意見を吸い上げて、その中から良さそうなところを取って、それを採用していくと。っていうのは、その日本人というのはね、これまた文化の違いだけれども、トップが決めたことを部下にやらせる、要するにトップダウンというのは日本の会社では難しいんだよね。どっちかというと、ボトムアップの方がみんな責任を持って、要するに自分たちが考えてやることになったわけだから、自分たちが一生懸命やらなきゃという気持ちを、あの当時は持つことが多かったのよね。だけど、今、アメリカの場合にはもう完全にトップダウンで「これやれー」って言うとみんなやってくる。日本の場合は上が決めたことなんかあれはまあしょうがない、しょうがないというかどうもね。やれることはやろうというね。そういう時代だったから。
高橋:わりと部下の方の意見も良く聞かれて一緒に、下から吸い上げていく形をとられたわけですね。
猪谷:そう。だけども、小泉さんみたいなのも、「あの人はあんまり人の言うことを聞かない」っていう話を聞いているけれども、しかしやっぱりねああいうリーダーでも人の言うことは僕は聞いていると思うわけよ。ただ、その発表の仕方というか、ポリシーの打ち出し方が違うんであってね。やっぱり人の言うことを聞いて、それを咀嚼した上で、こうやるからついて来いっていう、そういうリーダーじゃないと上手くいってる時はいいけど、一歩間違えると大変なことになる。
高橋:小泉さんは織田信長がロールモデルとおっしゃいますが、猪谷さんはどなたか。
猪谷:僕は誰だろうな。猪谷個人じゃないかな。
高橋:でも本当、ご自分で自分らしい生き方を作っていらっしゃるという。
猪谷:うん。
高橋:そういう感じがしますね。
猪谷:だから、例えばIOCでも、僕は公募都市の評価委員会という委員会、これは1966、7年の頃作ったのかな、評価委員会、それで僕は初代の委員長やったんだけれども、いろいろマニュアルを作ったりなんかもしてね、それが今、段々段々段々大きくなって今になっているんだけれども。あの当時はIOCの委員だけで評議委員を形成していたんだけれども、今はもういろんなところのスペシャリストを入れて30人ぐらいか、20人ぐらい大体なっているんだけれども。それで、僕は最後に委員長をやったのは2004年のソルトレイクの時だったかな。評価委員会の委員長をやって、その時にやっぱり20名ばかり韓国人、それこそ、14、5カ国からの委員で構成されている委員なんだけども、その委員長をやって、その時に本当にみんな良く仕事をやってくれたのね。そして、たまたま僕の前の評価委員長が小泉さんみたいな人だったのね。だから、結構中でいろいろフリクションがおきたりなんかして、それで僕はそれを見ていたものだから、よし、いつもの通りにやっていこうというのでやって、そしたら皆はとってもハッピーに、全部であの時は8ヶ国ぐらい立つんだったな。そして皆から感謝されたと思うけどね。やり方が変わっちゃうなんていうのはね。例えばこの会社もね、ここの創始者というのはある目標があるじゃないですか。そうすると、働いている人達はこのリーダーのためだったら自分たちはそれこそ火の中に飛び込んででもこの目標を達成しようとね。それが創始者だったわけね。僕を世話してくれた人ね。それからついこないだまで2代目のトップはこれはまたティピカルなアメリカ人でもうトップダウンなのね。そうすると結局社員たちは、働いている人達は、何を言っているんだ、このやろうってね。そんなこと言うんだったらやって見せてやるぞってね。結局行き着く所は同じなのよ、それが右の方から行くか、左の方から行くかっていうことなのね。リーダーっていうのはそういう2つのリーダーがある。
高橋:どっちがいいという訳ではない。
猪谷:それはない。やっぱりその人の個性によって。僕が小泉さんみたいなことをやっても決して成功しないと思うよ。僕についてきてもらうためにはやっぱり僕が持っているもんじゃないとね。借り物じゃ駄目だよね。