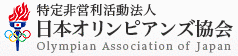- トップページ
- オリンピアンインタビュー
- 第23回 上村春樹さん
1976年7月31日、日本柔道界は悲願だったオリンピック無差別金メダルを手にした。地元開催だった1964年東京オリンピックで神永昭夫が体格差のあるヘーシング(オランダ)に抑え込まれ、銀メダルに終わったのを機に「パワー重視の柔道になった今、もはや日本が無差別で勝つのは難しい」という悲観論が強まっていた。それを一蹴したのが、当時旭化成に所属していた上村春樹。4
年前のミュンヘンオリンピックは国内予選1回戦で敗れ、代表候補に名前すら挙がらなかった男が、当時の世界最強といわれたチョチョシビリ(ソ連・当時)の怪力を完璧に封じて準決勝を勝ち上がり、決勝でレフムリー(イギリス)をあっさりと破ったのだから、日本中が驚かされた…。
現在は講道館長、全日本柔道連盟会長、そしてロンドンオリンピック日本代表選手団団長を務める上村が、紆余曲折の現役時代を振り返った。
上村春樹(以下、上村):「私は中学生の頃、1回も懸垂ができず、100mを20秒かかって走るような選手で、柔道で熊本県大会にも出ていません。そんな私を変えてくれた最初の指導者が、八代東高校時代の土谷新次先生でした。毎日道場に来る前にグラウンドを10周走ること、打ち込みを500本することを私に課したのです。今のオリンピック選手でも打ち込みは多くて1日に300本くらいしかやらないのに、15歳の自分に500本やれと言ったのはすごいこと。先生は視覚に障がいがあったので、すべてを音で判断した。いい投げ音がした時には『今の投げ方を忘れるな』と言うのです。それを自分の中に叩き込みながら反復しているうちに、自然と感覚が染みついた。高校生の頃にそれを体得できたのは大きかったと思います」
その後、上村は明治大学に進む。東京オリンピック柔道競技無差別の銀メダリストであり、明治大学で指導していた神永昭夫との出会いが、自分をより大きく変えるきっかけになったという。
上村:「大学入学早々の東京学生柔道体重別選手権1回戦で絞め落とされ、初めて試合をした講道館で長々と気絶したのです。柔道をやめて熊本に帰ろうと本気で考えました。そこに通りかかった神永先生が『春樹、人並みにやったら人並みにしかならない。素質のない者は2倍3倍やらなきゃ勝てないんだ』と…その言葉に感動して他の人より1日20分間だけ練習量を増やした。それを続けてやっと4年でレギュラーになり、学生選手権で優勝しました」
柔道でトップを狙うなら東京か大阪にいなければムリと言われたこの時代に、上村は九州の旭化成入りを決断する。「練習相手がほとんどいない環境に身を投じたことで、自然と自己調整する能力がついた」と彼は言う。エリート街道を歩まなかったことが逆に幸いしたのだ。入社1年目の全日本選手権で優勝したが、それを翌日の新聞に「上村、フロックで優勝」と書かれたことで、彼の負けじ魂に一気に火がついた。
上村:「『無差別の選手として174㎝・100㎏というのは小さすぎる。外国勢相手には通用しない』というのが私への評価でした。武器は何かと考えてみても、体も小さいし、スピードも力もない。しかし、それが自分の武器だと気づいたのです。スピードや力のない選手は逆に体が柔らかい。それをうまく使った柔道を作り上げようと思ったんです」
ある日、技の系譜を眺めていると、柔道の技の大半が前後に投げる技だと気づいた。自分の技を横に崩す形に変える努力も惜しまなかった。そんな成果もあって、1975年の全日本選手権で2度目の優勝を飾り、同年の世界選手権(ウイーン)でも金メダルを獲得する。しかし、全日本の準決勝で当たった同郷出身の高校生・山下泰裕が組み合うまで目をそらさなかったことで、非凡な才能を感じ、この若武者を倒すために別の武器が必要だと悟った。そこで上村は捨て身の小内刈りを1年かけて練習。翌76 年のモントリオールオリンピックの代表選考を兼ねた全日本選手権大会で勝って、本大会出場権を獲る。そして本番でも極めて冷静に相手を見ながら技を選択し続け、ついに無差別で金メダルを日本にもたらしたのである…。