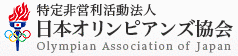- トップページ
- オリンピアンインタビュー
- 第27回 小野清子さん
【母として、選手として】
元川悦子(以下、元川):今日、お会いする前から、小野さんの経歴の素晴らしさについてカメラマンたちと話していました。
小野清子(以下、小野):選手として、モスクワの世界選手権やローマオリンピックなどに行って、これで一段落し、引退して家に入るつもりが、東京にオリンピックが来たがために人生を変えられてしまいました。子どもがいてまで、また逆立ちをしろというわけです。当時、普通は子どもを産んでまでスポーツをするなんて「バカじゃないの」と言われてしまう。だから、主人(小野喬氏)も呆れていましたよ。
2人目を産んだ1963年の夏、体操協会から「東京オリンピックに出てもらわないと困る」と強く要請されました。結局、体操は、若いから強いとか、元気がいいから点数が出るというわけではありません。技を持っていないと点数が出ないのです。技はそう簡単に力でできるものでもなくて、技術を身につけるのには時間がかかるのです。だから、技という財産を一つ持っている場合には、少しばかり年寄りでも体力と筋力が戻れば何とかやることができますからね。やるからといって必ず選手になれるわけではないのですが、主人から「やってダメならダメでいいんじゃないの、やることで若い人たちも育つのではないか」ということを言われて、「あぁ、そうか。自分が戻ることで少しでも日本体操界のためになるのであれば」と思い決心しました。
しかし、子どもを連れて練習へ行くと、平均台から落ちて危うく子どもに乗ってしまいそうになったり、跳馬の助走中に一緒についてこられたりと、なかなか競技に没頭できませんでした。
元川:今の時代の働いているお母さんたちみたいに保育所などに預けて、その時間は集中するというようなことはしなかったのですか?
小野:保育所などに預けてしまうと、本当に預けっぱなしになってしまいます。私の場合は、慶應義塾大学の授業は週2日で、他の日は時間に余裕があったので自分で面倒を見る時間がありました。ですから、普通のサラリーマンとして女性が働くときのように、朝から夕方までしっかり預けなければいけないという立場ではなかったです。人に預けるときは、「帰ったらいっぱい抱っこしてあげるからね」、「一緒にお風呂入ろうね」とか言いながら、何とか折り合いをつけてやっていました。本番の時は、オリンピック半月前の合宿から、私の母と姉たちが子どもの面倒を見てくれました。その期間は本当に集中できました。
元川:オリンピックが東京(日本)であるということは、大きなモチベーションになりましたか?
小野:東京で開催されたオリンピックに挑戦することができたということは、私の競技人生にとって良い意味でラッキーでした。また、挑戦したことで無事にメンバー入りできたということもラッキーでした。オリンピックの成績は、規定自由と4種目×2で失敗がゼロだったのです。大きな失敗もなく、粛々と自分の演技をし、それがチームの点数に全部活用されました。それ以上のことはできないし、それ以下もありません。また、スカッとすがすがしく終えることができたということは私の金メダルなのです。
元川:マスコミなどからの注目もすごかったでしょうね。
小野:脚一本上げるのを、カメラマンがズラッと並んで待っている状態でしょ。このようなことは過去に一度もありませんでした。そんな時、頭に浮かんだのが田中角栄さん(元首相)のこと。田中さんは外国の要人と会談を持つ際、内容を外に漏らさないために部屋に「もう一つのカプセル」を作って、その中で話をしていたというのです。私も演技をする時、自分の中にカプセルを作ることができればいいのではないかと考えました。そして本番は、直前まで他の選手の演技を全く見ないで、わが世界を作り上げ、自分の演技をしました。そうやって精神面をコントロールできたのは、長かった競技生活のおかげかなと思っています。