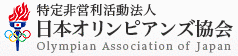- トップページ
- オリンピアンインタビュー
- 第10回 中村佳央さん 中村行成さん 中村兼三さん
【大きなプレッシャーの中での初のオリンピック】
広報スタッフ:3人での夢が叶ったアトランタオリンピックなのですが、実際にオリンピックに出場された時の気持ちや、その場で感じたことなどをそれぞれ教えていただけますか。
佳央:私の場合は、オリンピックに出場が決まって、それだけでも本当にうれしかったですね。実際のオリンピックの試合では、あれだけ「俺は日本人なんだ」と思ったことはそれまでになくて、期待される度合いが普通の競技とまったく違いました。「日本のために頑張らなければ」と、あんなに日本を強く感じたことはなかったですね。中にはせっかくオリンピックに出て、高い金を払ってアメリカまで応援の親戚を何十人と連れて来たのに、5秒か10秒で負けた選手もいたわけですが、その時は「うちは3人だから、俺が負けてもあと2人いるさ」という感じでした。「3人で出てよかった」と自分が思ったのは、1階級1日ずつだったのですが、私が兄弟で一番はじめに出て、会場の畳の滑り具合とか、審判はどんな感じだとか、会場は冷房が効いて寒いなとか、出場した自分でないとわからない情報をまだ出ていない2人の弟たちに教えることができたことですね。弟たちにも本当にメダルを取ってもらいたかったし、私が取れなかった分、兄弟のうち1人でも勝てば「よかったな」という気持ちを味わえるので、弟2人がメダルを取ってくれて、頑張ってきてよかったな、報われたなという気持ちがありましたね。自分1人だったら、負けてしまったことで何をやってるんだろうとか、なぜ勝てなかったんだろうと考えると思うのですが、兄弟3人が出られて、弟2人がメダルを取ってくれたことは救いみたいなところがありましたね。出られるだけでもうれしかったのですが、出るからには勝ちたかったし、その悔しさを弟が同じ会場で晴らしてくれたかなと。母親も「長男がよく面倒をみてくれたから、長男にもメダルを取らせたかった」と言ったんですけど、そういう経験が今は生きて選手を育てられているのかなというところもありますので、すべていい方向に…オリンピックを経験して、負ける悔しさとか勝つ喜びとかを全部経験できた。それもやっぱり兄弟が3人で出られたから、3人分を一気に知ることができた、教わったというのはありますね。
広報スタッフ:やっぱりオリンピックというと独特なものがありましたか。
佳央:やっぱり世界中の注目が違うんですよね。また、自分もオリンピック選手という名前をもらえるわけです。自分ら3人の場合は、それぞれスター選手ではないですが、4年に1回のオリンピックに3人でということはあり得ないと思われていたので、3人で出たことによってすごい注目を浴びたんです。ここまで注目されることもなかったので、自分たち兄弟は今まで習ったすべての力を出して戦ったのですが、それがうまくいく選手もいますし、負ける選手もいるので、そういうところでまた一つ学んだようなところもあって、本当に人間的に大きくなったなと思います。
行成:僕も、やっぱりどの大会よりも緊張しましたね。前の日に、柔道のことばかり考えて、対戦している相手とのイメージがずっと頭に出てなかなか眠れないということがありました。3人で出ているわけですから、最悪のことを考えるんです。「3人が3人ともメダルも取れなかったらどうするんだ、何を言われるかわからない」とか。3人で出てすごいんですが、逆に3人が悪い成績だとどれだけのことを言われるのだろうという不安感も大きかった。プレッシャーはありましたね。
佳央:全世界の期待感、そういう見えないものの中で勝っていくうれしさとか、国を挙げて来ているところに打ち勝っていったうれしさだとか、負けた悔しさだとか、そういうものが渦巻いているので、何が起きるかわからないというか。何をしてくるかもわからないし、オリンピックにはそういう見えないものがありますね。それだけ期待して、注目も高いから、国もバックアップするのだろうし、自分たちも頑張らなければいけないというところもあるので、本当に3人で出ていなかったらつぶされていたかもしれないですね。
【3人で戦ったオリンピックの舞台】
広報スタッフ:実際に試合場に立った時の感覚というのはどうでしたか。
行成:始まれば…実際に組んで1回戦が終わってしまえば、リラックスして普通に戻れるんですが…問題は一発目なんです、何の試合でも。何か波乱が起きるといったらたぶん1回戦です。それだけずっと考えて、緊張しているわけですから。オリンピックという期間中は余裕がなかったですね、会場にいる時はずっと気を張りっ放しでした。柔道というと、日本の選手をどうやって倒そうかと世界中が狙ってくるわけでしょう。何をやってくるかわからない。だから、あまり知らない選手だとすごく不安なんです。オリンピックでチャンピオンになるんだったら日本の選手に勝たないといけないと、どこの世界の選手も考えてくるから研究されている。まぁ、自分の柔道をやらせる前にバーンと攻めて、ポーンと一本を取れば早いのですが、こっちも慎重になるじゃないですか。ポカやっちゃいけないとか思うし(笑)。
広報スタッフ:やっぱり悪いほうに考えてしまうことはありましたか。
行成:ありますね。僕は気が強いと言われるけれどそう見せないだけであって、小さい時から柔道の先生に「試合中は痛いところがあっても顔に出すな。相手にばれるだろう」と言われてやらされていましたから、少しでも弱いところを見せたらいけないと思ってやっていますが、心の中はもういろいろ考えていますよ、どうしよう、どうしようって。
佳央:1年、1年で実力が変わってきますからね。上り調子の時しか知らなかったんですよ、オリンピックまで。私の判断では、オリンピックはちょうどピークから若干落ちたぐらいかなと思います。兼三はピークでしたね、絶好調でした。
行成:やっぱり不安があったんでしょうね。勝つ時はどこかに自信があるんですよ、負ける気がしないという。1995年の幕張の世界選手権は決勝戦で負けたんですが、その選手とまた決勝だったんです。負けた選手というのはどうしても意識してしまう。相手のことを逆にこっちも研究するわけです。それで相手のことを知りすぎてどうしても様子を見てしまって、逆に自分の味が決勝は消えたかなと…これぐらい攻めていたら勝てるんじゃないかと自分の中で判断して、一か八かという本当の勝負はできなかったですね。だから試合が終わって、自分の中で「際どいけれどももしかして勝ったかな。でも、最後にちょっと腹ばいに倒れたからどうなのかな」と計算した。その辺を考えず、本当にがむしゃらな勝負をはじめからやっておけば変わっていたと思うんですけど。
広報スタッフ:ちょっと考えすぎてしまったんですね。
行成:考えすぎました。でも、僕の中では負けていないだろうと今でも思っています。結果はずっと一生残りますが、世間では一番下の弟と真ん中の区別がつかないから、いつも「オリンピック優勝おめでとう」と言われるんです(笑)。「ありがとう」と言いますが、僕も優勝と思っています。
佳央:私は外から見ていて、はじめから行かせたかったわけです。でも、やっぱり実力とか、その日の調整具合とかで本人が決めるわけなので。そこにガーッと言ってしまったところもありますし、「言わないと勝てない、勝たせてやりたい」と思ったところもあるんですよね。本当にこの3人の試合で一気にすべてを見たかなというのがありますね。
広報スタッフ:兼三さんは、勝ち続けて代表を取って本番という形でしたし、大舞台も初めてということでしたから、怖いもの知らずという感じで臨めた大会だったのでしょうか。
兼三:そうですね。そういう点で言うとプレッシャーというのはあまりなかったですね。兄2人は世界チャンピオンという実績もありますが、自分は初出場ですし、それまで注目されていませんのでプレッシャーなく試合に臨めたのですけれども、自分の中では自信があっても、みんなが言うように魔物が棲むとか、何かあるのではないかという不安はありました。1回戦を勝ってしまったらそういうのが徐々になくなってきて、大げさですが、ちょっと楽しむことができたのではないかなと思います。
広報スタッフ:やっぱりお兄さんの分も、みたいな気持ちはありましたか。
兼三:そうですね。それまでの柔道の競技で前日に女子の恵本裕子さんが優勝したのですが、男子では金メダルがなかったので、兄弟でもそうですし、やはり日本の柔道というところからも、自分が金メダルを取らないといけないという気持ちはありました。